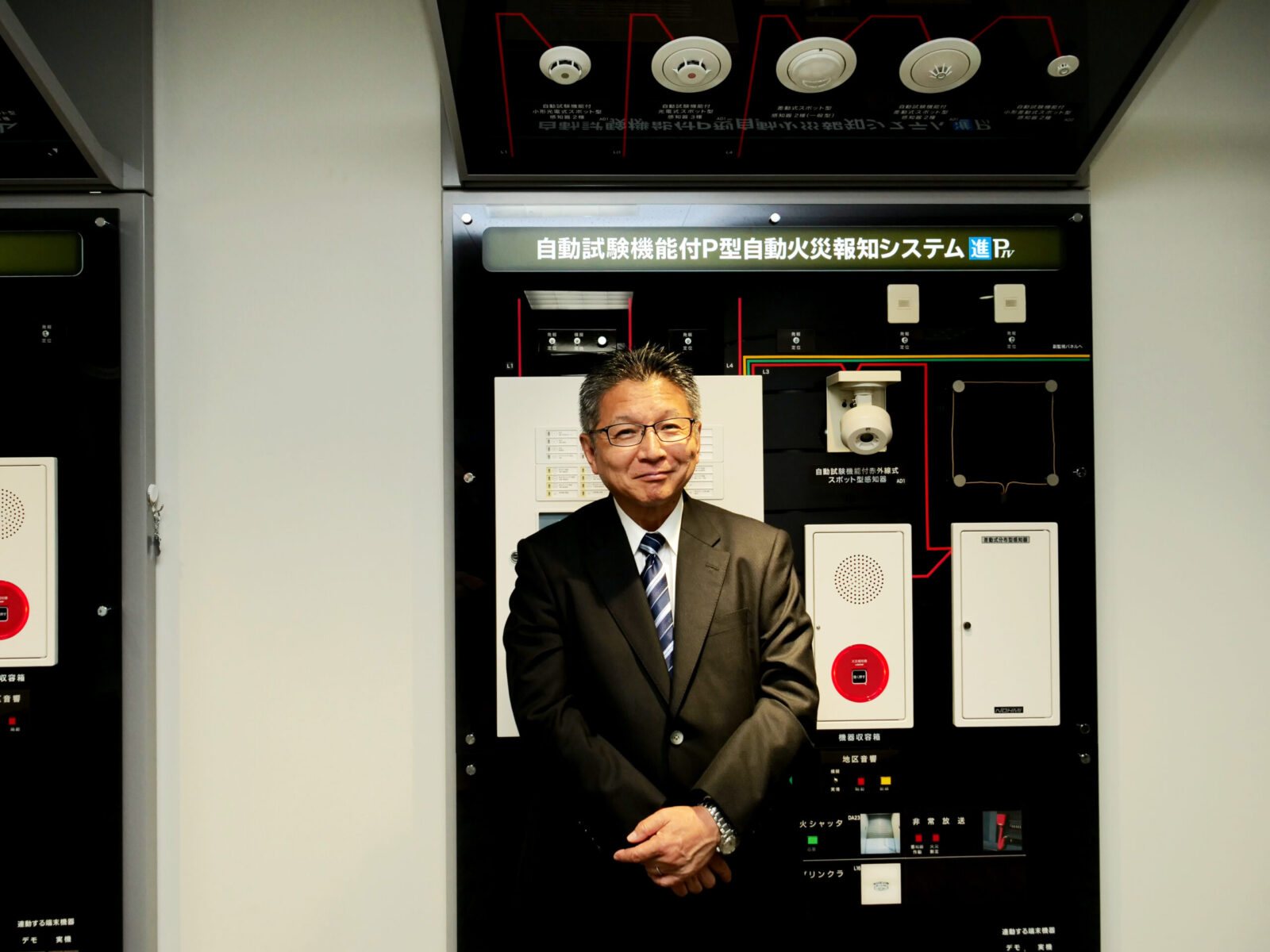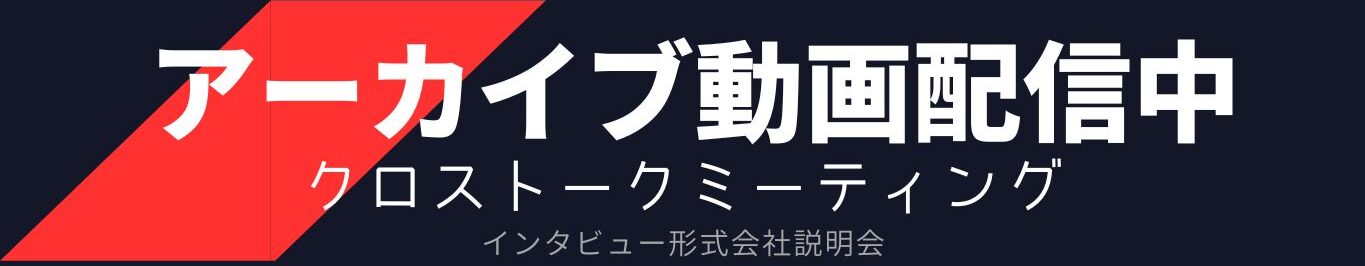長野計器が現在未来を見据えて挑んでいるのが、新エネルギー分野である。同社は経済産業省が所管する国立研究開発法人NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の水素関連プロジェクトにいち早く参画し、同分野での開発に取り組んできた。
水素の身近な使用例として自動車が挙げられる。同社では、水素を「①つくる・貯める」「②運ぶ」「③ステーション」「④車」の4段階で製品を提供している。
① つくる・貯める
水素製造は、化学プラントで副次的に発生する水素の回収、化石燃料や木質バイオマスからの製造、冷蔵庫サイズの小型装置による製造などの方法がある。製造した水素の貯蔵には気体の圧縮が必要で、圧縮時の圧力モニタリングに同社の計測器が用いられている。水素には材料を脆化させる特性があるため、同社では水素脆化に対応した特殊材料を用いた計測器を開発、長期使用に耐えうる製品を世に供給している。
② 運ぶ
国内の水素製造量は少なく、サプライチェーン構築には輸送が必要だ。水素は液化すれば体積が800分の1になるため、大量輸送には液体水素での運搬が有力視される。ただし水素はマイナス253度で液化するため、極低温輸送が必須である。同社では宇宙開発関連機関での検証を行い、24年に業界に先駆けて液体水素の直接計測が可能な圧力センサ(極低温計測)の開発に成功した。現在液体水素の輸送・搬送関連企業とも取引を行い、各社と協働で実証実験を続けている。
③ ステーション
国内の水素ステーションは全国157カ所(24年9月時点)で、政府は30年に1000カ所を目標としている。国内のステーションに設置されている水素の圧縮機や貯蔵タンク、ディスペンサー(自動車に水素を充填する機械)のうち、大半で同社の圧力計器が採用されている。ディスペンサーから自動車に充填される水素は、1㎝四方1200㎏の超高圧。そのため圧力計器も、高圧水素に対応した専用品を取り揃えている。
④ 車
14年からトヨタ自動車の燃料電池自動車(電気自動車の一種で、水素と酸素の化学反応で発電した電気で駆動する)「MIARI(第1/第2世代)」に同社の圧力センサが搭載され、続いて新型クラウンセダンFCEVモデルにも採用された。計測器は車両性能にとって重要となる高圧水素タンク及びスタック(発電装置)への水素圧力の監視機能を担っており、こちらでも1cm四方700kgの超高圧に対応している。
さらに、MIRAIのFCシステムはフォークリフトやFCバスなどに展開され、用途が拡大してきている。
新エネルギー分野は社会的に実証実験の段階にあり、現在携わる企業はほんのひと握りである。そんな中、同社では業界に先駆けて水素やアンモニア分野での技術革新に取り組んできた。新エネルギーが社会実装され、開発が脚光を浴びる日も近いと見られる。
超高圧から極微圧まで
長野計器の創業は明治29年。圧力計や圧力センサを中心とする各種センサなどの精密機器を開発・製造・販売。圧力計は国内シェア60%を占める。近年では半導体向け、FA・産業機械向け製品が伸長している。